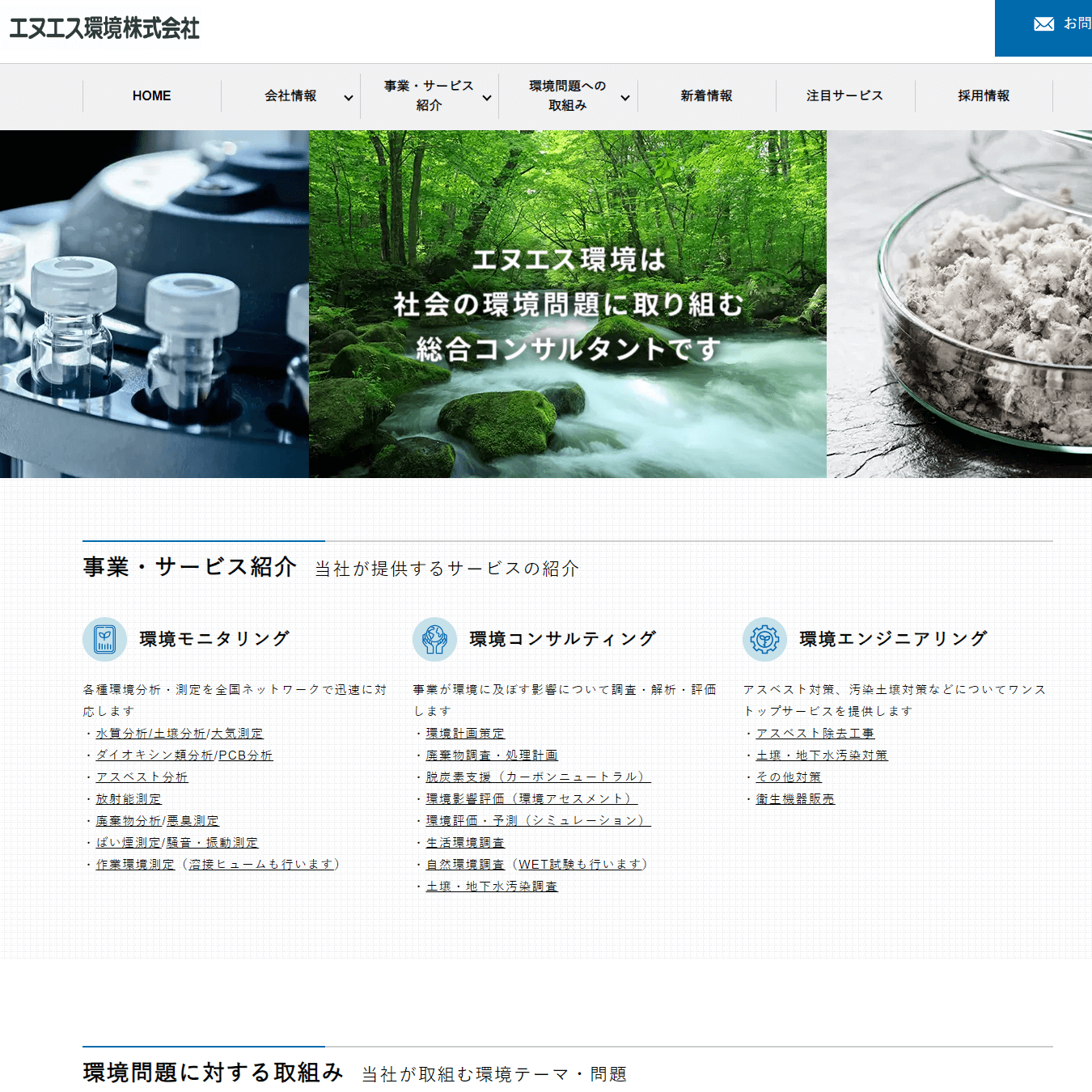アスベストは、かつては多くの建物の建材として使用されていました。しかし、ある時期を境に規制が入り、今では使用を禁止されています。その理由は、アスベストが引き起こす健康被害によるものです。本記事では、アスベストの歴史をたどっていきます。アスベストがどのような背景から規制されていったのか、知るきっかけになれば幸いです。
目次
アスベストが使用されていた理由
アスベストは、耐火性、断熱性、防音性、絶縁性などに優れ、さらに化学薬品にも強いという特性を持っています。これらの特性により、アスベストは建材や工業製品に多く使用されてきました。その上、安価で手に入ることもあり、広範囲で利用されたのです。
アスベストが使用されていた場所は、多岐にわたります。住宅や倉庫では外壁や屋根、煙突、軒裏などに使用され、ビルや公共施設では鉄骨の構造部分、天井や壁、床の下地などに使われていました。これらの建材には吹き付け材や成形材、耐火被覆材、断熱材、吸音材などとして利用されていたのです。
さらに、アスベストは工業製品にも広く使用されていました。具体的には、自動車、冷蔵庫、エアコン、トースター、洗濯機などの日用品に加え、ブレーキやパッキン、ガスケット、絶縁材など、多くの部品にも利用されていたのです。これらの製品においてアスベストは、摩擦材やシール材、絶縁材などの役割を果たしていました。
経済産業省の調査によると、2005年時点で185社774製品にアスベストが使用されていることが明らかになっています。このように、アスベストはその特性を活かして様々な製品や建材に使われてきましたが、健康への影響が明らかになったため使用が禁止されることとなりました。
アスベストが禁止になった時期
アスベストの使用禁止は、長い時間をかけて段階的に進められました。その流れと時期を、以下に紹介します。
1960年にじん肺法が施行
1960年に「じん肺法」が施行され、アスベストによる健康被害への対応が始まりました。しかし、この法律の施行から完全な使用禁止に至るまでには、約30年ほどかかりました。
その後のアスベストの規制の流れ
最初の規制は、1975年に行われました。特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有率が5%を超える建材の吹き付け作業が原則禁止されたのです。その後1995年には、同規則の改正で、石綿含有率が1%を超える建材の吹き付け作業が禁止されました。
さらにアモサイト(茶石綿)とクロシドライト(青石綿)の使用も禁止されたのです。その後、2004年には、石綿含有量が1%を超える建材や摩擦材、接着剤など、10品目の製造・輸入も禁止されました。
そして、2006年には、石綿含有量が0.1%を超える製品の製造、輸入、使用が原則禁止となったのです。ただし、一部製品には猶予措置が設けられました。
アスベストが原因で起こる疾病とは
アスベストの繊維は非常に細かく、空気中に飛散しやすいです。これを吸い込むことで肺の組織内に沈着し、長期間にわたって滞留します。このような状態が続くと、様々な深刻な疾病を引き起こすとされています。アスベストが原因で発症するとされる代表的な疾患は、以下の5つです。
石綿肺(じん肺)
石綿肺は、粉じんを吸入することで肺が線維化する疾患の一つです。初期症状としては、せきやたん、息切れが現れます。
病気が進行すると、重度の息切れや呼吸不全を引き起こし、最終的には日常生活に大きな支障をきたすのです。アスベストを長期間、大量に吸い込むことで発症することが知られており、作業環境でのばく露が主な原因とされています。
肺がん(原発性肺がん)
原発性肺がんは、気管支や肺胞を覆う上皮に発生する悪性腫瘍で、アスベストとの関連が強いとされています。主な症状には、せき、たん、血痰、胸痛、息苦しさなどがありますが、病気が進行するまで自覚症状がほとんど現れない場合もあります。
アスベストに長期間さらされることが肺がんのリスクを高める要因となり、とくに喫煙者においてはそのリスクがさらに増すことが分かっています。
悪性中皮腫
悪性中皮腫は、胸膜、心膜、腹膜などの表面を覆う細胞層にできる悪性腫瘍です。症状としては、せき、胸の痛み、呼吸困難、胸部圧迫感に加え、発熱や体重減少がみられることもあります。アスベストを吸引することが主な原因であり、その他の原因で発症することもあります。
びまん性胸膜肥厚
びまん性胸膜肥厚は、肺を覆う胸膜が線維化して厚く、硬くなる病気です。線維化が進行することで呼吸機能が低下し、息切れや呼吸困難が見られるようになります。
この病気はアスベストの長期的なばく露が原因となり、肺がんや悪性中皮腫と並ぶアスベスト関連疾患の一つです。進行すると治療が難しくなるため、早期発見が重要です。
良性石綿胸水
良性石綿胸水は、肺を覆う胸膜やあばら骨内側に炎症が起き、胸水がたまる病気です。症状としてはとくに現れないことが多く、胸水が自然に消失することが一般的です。
しかし、場合によっては胸水が消失せず、呼吸器障害が残ることもあります。この疾患もアスベストの影響によって引き起こされるもので、場合によっては後に悪性腫瘍に進行することもあります。
まとめ
アスベストはその優れた耐火性や断熱性から多くの建材や工業製品に使用されてきましたが、健康被害が明らかになり、段階的に規制が進められました。1960年のじん肺法施行を皮切りに、1995年には石綿含有率が1%を超える建材の使用が禁止され、最終的には2012年に全面的な使用禁止に至りました。アスベストが引き起こす疾患には、石綿肺や肺がん、悪性中皮腫などがあり、早期発見と対処が重要です。健康被害を防ぐためには、適切な規制と監視が不可欠です。
-
 引用元:https://northk.jp/lp/
引用元:https://northk.jp/lp/