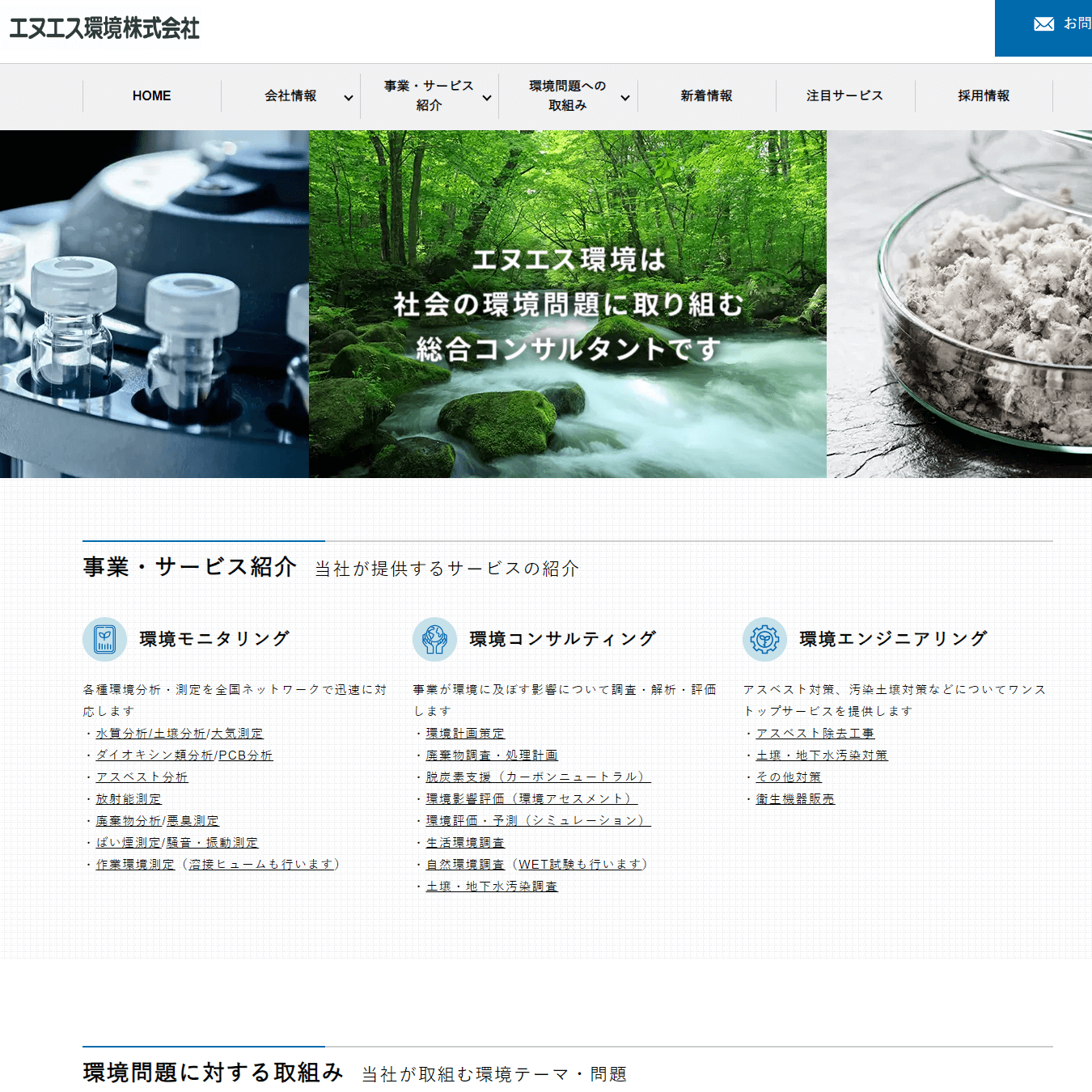建築業界で働く人や、工事現場の周りで生活する人々に健康被害を出さないように厚生労働省が定めているのが石綿障害予防規則です。段階的に法改正を重ねてすべての建築物や一定規模以上の解体・改修工事について石綿の有無の事前調査結果の報告が義務化されました。この記事では、アスベスト法改正でなにが変わったのかを徹底解説します。
アスベストとは
アスベストは、石綿鉱石から採掘される繊維状のケイ酸鉱物で、耐熱性と耐火性に優れているのが特徴です。昭和30年くらいから建築材料や断熱材として、さまざまな建築物などで使われてきました。
アスベストのリスク
アスベストを吸い込んでしまうと、健康面で非常にリスクが高いです。微細なアスベスト繊維を吸い込んで肺に入ってしまうと、なかなか外に出ることはありません。
そのため、慢性的な呼吸器疾患や、石綿肺・肺がんなどの疾患が発症する可能性が非常に高くなってしまいます。アスベストに関しての疾患は、アスベストにばく露してから長い年月を経てから発症すると言われています。
たとえば、中皮腫は平均35年程という長い期間潜伏したあとで発病するパターンが多いです。
アスベストに関する法規制
2021年に大気汚染防止法の改正があってから段階的に、アスベストの規制が強くなっています。アスベストに関する法規制によって、刑事罰や罰金なども科せられる可能性もあるでしょう。
大気汚染防止法
大気汚染防止法とは、日本における大気汚染の防止を目的とした法律です。産業活動や自動車の排出ガスなどによる汚染物質の規制を行い、健康と生活環境を守るために改正をしてきました。大気汚染を防止するための法律ですが、健康に悪影響を及ぼすような粉塵なども規制対象です。
アスベストの事前調査が法定化されたことにより、報告義務や有資格者しかアスベスト調査ができないなどの決まりができました。
石綿障害予防規則
石綿障害予防規則は、アスベストからの健康被害を防ぐための目的で制定された日本の規則です。建設業や解体業に従事する労働者を対象に、石綿の飛散を防ぐための厳格な管理基準が設けられています。
この規則によって事業者は作業前に石綿の有無を調査して、適切な防護措置を講じることが義務になっています。アスベストが気化しやすいような作業環境では、最適な換気システムなどの設置が大切です。
また、石綿が使用された建物の解体時には専門的な処理を行うことで、周囲への健康被害を最小限に抑えられます。解体の際には、それらの処理が必ず求められます。
廃棄物処理法
廃棄物処理法とは、廃棄物の適切に処理することで環境保護を目的とする基本的な法律です。産業廃棄物や一般廃棄物の収集・運搬・処分について厳格な規制を設けています。
この法律は、廃棄物が不適切に処理されることによる環境汚染を防ぎます。アスベストを含んでいる廃棄物などは、廃棄物処理法に基づいて適切な取り扱いが必要です。アスベスト含有廃棄物に関しては、厳格なガイドラインがあります。
このガイドラインは、万が一にでもアスベストが環境に放出されることを防いで、人々の健康と環境を守るために重要です。事業者は、アスベスト廃棄物を適切に処理する目的で許可を取得して、決められている流れに沿って作業を行う必要があります。
労働安全衛生法
労働安全衛生法とは、日本の労働者の安全と健康を守るために制定された法律です。この法律では、職場での労働災害の予防や健康管理の基準を定めています。事業者に対して安全な作業環境の整備や労働者の健康診断の実施、適切な安全教育の提供を義務付けています。
労働安全衛生法は、作業場などでアスベスト曝露のリスクを軽減するための基準を設けているのも特徴です。そして、労働者自身も安全に配慮してアスベスト被害を未然に防ぐ責任があります。アスベストに関連する健康の被害があるかもしれないケースなら、労働者は職業病として報告することが可能です。
雇用者は、労働者が職業病という報告をした場合に、事業主は改善するために適切な対応を取ることが必要になります。
アスベスト作業に関しての法改正の内容
アスベスト作業を行う上で、作業者や周辺住民の健康被害を起こさないために、大気汚染防止法が改正されました。ここでは、アスベスト作業に関しての法改正の内容について詳しく紹介します。
作業結果の報告義務付け
アスベスト除去の作業を行う際のアスベストの取り残しを防止する目的で、令和3年4月1日に作業結果の発注者への報告の義務付けが法律で施行されました。必要な知識を持っている方からの作業終了の確認が必須になり、作業記録を保存することも法律で義務化されています。
作業基準遵守義務の対象者拡大
短期間での工事のケースで命令を実行する前に工事が終わってしまわないように、令和3年4月1日に下請け業者も作業基準遵守義務の対象者としました。作業基準遵守義務の拡大によって、元請業者だけではなく下請業者も特定建築材料や特定粉じん排出等作業の種類ごとに作業基準を遵守する必要があります。
新たに直接罰の追加
令和3年4月1日にアスベスト作業を行う際に、直接の罰が下されるようになりました。アスベスト作業で直接罰になるケースは「危険度が高いアスベストレベル1に分類される吹付けアスベストの除去作業を行う際に隔離をしないで作業をした場合」です。
アスベスト法改正のポイント
アスベストによる健康被害を防ぐために、平成17年に石綿障害予防規則が制定されています。改正の主な内容としては建物の解体・改修時における石綿の事前調査が義務化されて、違反した場合には罰則が強化されました。
この規則では、作業を始める前にアスベストの含有の有無を事前に調査することや、建築物などの解体・改修工事を行う際に適切な措置を講じることが義務付けられています。しかし、これらの措置が適切に行われていないケースも確認されているのが事実です。
そのため令和2年7月に石綿障害予防規則が改正され、健康障害を防止するための対策が強化されました。
石綿含有の事前調査
石綿含有の事前調査は、建物の解体や改修工事を行う際に極めて重要なポイントです。最新の法改正により、石綿(アスベスト)が含まれている可能性がある建物については、工事前に専門資格を持っている技術者が事前調査を行うことが義務付けられました。
この調査結果は、適切な処理計画の策定や安全対策の基礎となり、工事中の石綿飛散リスクを減らすために不可欠です。違反時には厳しい罰則が科されることから、事業者は法律の遵守が必須になっています。
吹付け石綿・石綿含有保温材の除去工事
吹付け石綿・石綿含有保温材の除去工事は、作業者と周囲の安全を確保するために厳格な規制が導入されました。改正法では、これらの石綿含有材料を除去する際に、事前調査の結果に基づいた作業計画を作成して厚生労働省に届け出ることが義務付けられています。
除去工事は専門的な技術を持っている作業者が行い、作業エリアの封じ込めや適切な防護措置を行う必要があります。また、石綿の飛散防止策が徹底され、工事後の検査により安全が確認されるまで厳しい管理が続けられるのも変化したポイントです。
石綿含有成形板等・仕上塗材の除去工事
石綿含有成形板等・仕上塗材の除去工事では、作業の安全性を強化するために新たな基準が設けられました。改正法によって石綿含有の成形板や仕上塗材を扱う際には、専門的な事前調査が必要となり、その結果に基づいた安全管理措置が求められます。
除去工事では、石綿の飛散を防ぐための徹底した封じ込めと、適切な防護具の使用が義務付けられています。そのため、作業終了後の空気中の石綿濃度測定も必要です。これにより、作業者および周囲の住民の健康リスクをさらに抑えることができます。
作業実施状況の記録
令和3年4月から、工事作業を行なった状況を写真にて記録して、3年の間は保存する義務が発生します。アスベストを含んでいる建物や工作物などの解体・改修工事は、作業を行なった状況がわかるように写真を残しておく必要があります。
労働基準監督署への届出
工事前に労働基準監督署へ届出を行う際は、令和3年4月から吹付石綿やアスベストを含む保温材の除去工事の場合、14日前までに労働基準監督署へ届け出る必要があります。また一定の基準を超える建築物や特定の工作物の解体・改修工事に関しては、電子システムを利用して事前調査の結果を提出する必要があります。
アスベスト法改正後の工事の流れは?
アスベスト事前調査の具体的な変更点
工事を実施する前には、解体や改修の対象となる建築物や設備について、アスベスト含有の有無を確認する事前調査が必要です。
改正後、事前調査は次の3つの方法が義務付けられました。
設計図書の確認による書面調査
工事対象の建築物や設備について、設計図書や仕様書を用いて過去の情報を確認してください。これは、使用されている建材の種類や位置を把握する目的があります。
現地確認による目視調査
実際に現地に赴き、建材の状況や特定の部材を目視で調査しましょう。これにより、書面調査だけでは判断がつかない部分を補足します。
不明材料の採取と分析調査
アスベスト含有の有無が不明な場合、建材の一部を採取し、専門機関で分析調査を行う必要があります。とくにアスベストの存在が疑われる箇所では、正確な分析を行わなければなりません。
調査結果の保存と新たな義務
改正法では、後から必要な際に調査結果を確認できる体制を整備するために、アスベスト事前調査の結果を記録し、最低3年間保存することが義務化されました。
また、アスベスト含有建材の除去工事を行う場合には、作業計画書の作成がすべてのレベル(レベル1~3)で必要となり、計画の透明性と安全性が重視されています。アスベスト含有建材は、飛散性の程度に応じて以下の3つのレベルに分類されます。
以下で、レベル1~3についてそれぞれの特徴を確認しましょう。
レベル1:高飛散性建材
対象は「石綿含有吹付け材」で、飛散性が極めて高く、作業者への健康被害リスクが、もっとも高い建材です。主な使用場所は、建築基準法に基づく、耐火建築物の柱や梁などに多いとされています。
レベル2:中飛散性建材
対象は「石綿含有保温材」「耐火被覆材」「断熱材」などで、飛散性が高いとされています。ボイラーや配管、空調ダクトなどに多く使用されていた種類です。
レベル3:低飛散性建材
レベル3は、レベル1と2以外の石綿含有建材が該当します。具体的には「石綿含有成形板」などで、建材に石綿が練り込まれており、飛散性が比較的低いとされます。主な使用箇所は、天井や壁、床などです。
このように、アスベスト除去工事を行う前には、事前調査を確実に行い、正確な結果を基に安全な施工計画を立てることが求められます。
アスベスト除去工事中における新たな規制とは?
工事前の事前調査だけでなく、アスベスト除去工事中の作業基準も大幅に見直されています。この改正は、作業環境の安全性を確保し、健康被害を防止するための重要な措置です。以下で、詳しく解説します。
レベル3建材の新たな規制対象化
先ほど、レベル1~3について紹介しましたが、これまでの規制では、飛散性が高い「レベル1」と「レベル2」の除去作業に対してのみ厳しい作業基準が適用されていました。
しかし、法改正により、飛散性が比較的低い「レベル3」も規制対象に追加されています。この変更に伴い、レベル3建材の除去作業時にも具体的な作業基準が定められ、安全確保のための対策が求められるようになりました。
この改正により、従来の規制範囲を超えてアスベストの安全管理が強化されることとなったのです。
罰則の新設と強化
改正後の法規では、アスベスト除去作業基準を違反した場合の罰則が大幅に強化されました。従来は、行政命令を経て、その命令を無視した場合にのみ罰則が科せられていましたが、現在では直接罰が新設されています。
まず、作業基準違反者には、行政命令を経ずに、3か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられることとなりました。
さらに、改正前は元請業者のみが罰則の対象でしたが、改正後は下請業者も対象に含まれるようになり、すべての工事関係者が責任を共有する形へと変更されています。
これらの強化された罰則は、法規制の遵守を徹底させるためのものであり、安全基準を無視する行為への抑止力となるでしょう。
以上のことから、法改正の内容を正確に理解し、適切な作業手順を守ることが必要不可欠です。法改正をきっかけに、すべての工事現場で安全と健康を最優先に考えた対応が求められています。
工事完了後に求められる新たな規制とは?
アスベスト除去工事が完了したからといって、すべてが終わるわけではありません。工事後の確認や記録の作成、報告に関する規制が強化され、作業完了後も責任を持った対応が求められます。以下では、改正された規制の詳細について解説します。
専門資格を持つ者による作業完了後の確認
工事が終了した後、アスベスト含有建材の取り残しがないか確認することが義務付けられています。この確認は、専門知識を持つ「知識を有する者」が行う必要があります。
2023年10月以降、この「知識を有する者」は以下の3ケースです。
・一般建築物石綿含有建材調査者:一般的な建築物におけるアスベスト含有建材の調査を行う専門資格者。
・特定建築物石綿含有建材調査者:特定の条件下で設計された建築物に対応する高度な専門資格者。
・一戸建て等石綿含有建材調査者:一戸建て住宅や共同住宅の住戸内部に特化した調査を行う資格者。
なお、2023年10月以前に「日本アスベスト調査診断協会」に登録されていた者も「同等の知識を有する者」として認められており、この役割を担うことが可能です。
これにより、作業完了後の確認精度が高まり、取り残しによるリスクを最小限に抑えることが期待されています。
特定粉じん排出等作業記録の作成と保存義務
改正法では、アスベスト除去工事に関する記録作成と3年間の保存が義務付けられました。この作業記録は、特定粉じん排出等作業を行った際の詳細な作業状況を記録したものです。
なお、特定粉じん排出等作業とは、アスベストを含有する建築物や設備を解体、改造、または補修する作業を指します。これらの記録は、将来的な確認やトラブル発生時の対応に役立つ重要な資料となります。
発注者への報告義務と報告書の保存
アスベスト除去工事が完了した後、工事の実施状況に関する概要を発注者に報告することが新たに義務付けられました。
この報告は書面で行う必要があり、その報告書は少なくとも3年間保存することが求められます。この報告義務により、発注者は工事の透明性を確保し、リスク管理を行うことが可能です。
同時に、施工業者側も適切な対応を取った証拠として報告書を活用するという目的も果たします。
2021年(令和3年)4月の法改正後も続く新たな規制追加
健康と環境を守るために、アスベストに関する規制は2021年の大改正に留まらず、さらに厳格化されています。
以下で、2022年から2023年にかけて追加された新たなルールについて詳しく見ていきましょう。
2022年(令和4年)4月に義務化された事前調査結果の報告
2022年4月1日から、アスベストの事前調査結果を行政に報告する義務が追加されています。
なお、報告は「石綿事前調査結果報告システム」を通じて電子申請で行う必要があります。これは、紙面による申請の手間を省くと同時に、データの正確な管理を可能にするものです。
この報告義務は、アスベストの危険性を段階別に分類したレベル1からレベル3まで、すべての対象物に適用されます。この義務化により、行政はより詳細な情報を把握し、地域の安全対策に役立てることが可能になりました。
また、事前調査の報告を通じて、工事業者が適切な作業基準を守るよう促す仕組みとなっています。
2023年(令和5年)10月に導入された「知識を有する者」制度
こちらは、先ほど専門資格を持つ者の項目で解説しましたが、実は2023年10月1日以前では、建築物や建材のアスベスト含有の有無を調査する際に特定の資格が必要とされていませんでした。
現在では「一般建築物石綿含有建材調査者」「特定建築物石綿含有建材調査者」「一戸建て等石綿含有建材調査者」「2023年10月以前に日本アスベスト調査診断協会に登録されていた者」のみが作業完了後の確認を行えます。
また、資格者による調査が義務化されたことで、アスベスト取り扱いにおける専門性が高まり、取り残しや誤認のリスクを減少するという目的があります。
これらの取り組みにより、工事現場におけるアスベスト対策がより強化され、工事関係者や周辺住民の安全が確保されています。今後も法律の改正や追加が行われる可能性があり、工事業者や関係者は常に最新の規制に対応する必要があります。
まとめ
アスベストを吸い込んで肺に入ってしまうと、なかなか排出されることはないので、深刻な健康リスクをもたらす危険な物質です。2021年に大気汚染防止法の改正があってから少しづつアスベストの規制が強くなっていて、法規制による刑事罰や罰金なども科せられる可能性もあるでしょう。
アスベスト作業に関しての法改正の内容は、アスベスト作業を行うときに、作業者や周辺住民に健康被害を出さないよう大気汚染防止法が改正されています。
アスベストに関する健康障害の予防対策の推進を図るために、平成17年に石綿障害予防規則が制定されました。また、石綿障害予防規則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査や、建築物などの解体・改修工事で必要な措置が実施されていない事例が確認されています。
-
 引用元:https://northk.jp/lp/
引用元:https://northk.jp/lp/